あぶない山屋、古田学さんのこと。
Juni 23, 2010
今回、exblog から一番最後に移行させた記事はこの記事です。
もうかれこれ9年ほど昔のことになるが、大晦日の晩に、御座石鉱泉からアカヌケ沢の頭を目指して登っていったことがあった。西平という地名だったと思うが、あのあたりに遭難碑があった。
真夜中にこういうものの前を通過するときには、見て見ぬ振りをするときもあるし、あるときは遭難碑に(心の中で)話し掛けたりもする。 そのときも、そうだった・・。
「これからアカヌケに登って、朝日に染まるバットレスの写真を撮りにいって来るんだけれど、一緒に登るかい?」 そう心の中で思って、右手で辺りの空気をぐっと握り締めた。
数ヶ月前、単独登攀の記事を検索していると、「新☆あぶねえ山屋のページ」を見つけた、いわゆるZ式の単独登攀の方法などなかなか教科書的な本には書かれていない技術が書いてあり、私もワルテル・ボナッティの本を読んで以来同じようなことを考えていたので世の中には、似たようなことを考える人がいるものだなと感じた。
何度か記事に目を通すうちに、2003年11月8日で記事更新が終わっているのが気になった。
もうネット上に記事を公開することを止めてしまったのかな?とも思ったが、ほかの方の記事から、管理人の古田学さんは、妙義山の星穴岳というところで帰らぬ人となったとのこと・・。
僕は、そうか・・と思い、こうした先鋭的な登山を繰り返すクライマーのありうべき結末のひとつとして冷静に受け止めていた。
ホームページを見ると一目瞭然であるが、古田さんは凄い実践力をお持ちの方でその登山歴には、目を見張ってしまう。
僕と同世代で、同じ頃に登山をはじめたようだが、私がいまでも奥秩父のしょぼい、ちんけな山々を相手にふーふー言っているのに比べ、この方は80年代後半から、90年代にわが国の名だたるルートをほとんど単独で登ってしまったのであるから、たいしたものである。
お亡くなりになった2003年の11月16日に僕は何をしていたかな・・?なんて思うとともに、星穴岳に一度行ってみたいと思うようにもなった。
古田さん(面識はないが、国立あたりにお住まいだったようで、どことなく親しみを感じるのでこう呼ばせていただく)は、たぶん、さほど知られていない星穴岳でご自身が命を落とすことになるとは、予想だにしていなかった筈である。その11月の上旬に登られた前穂の北尾根のほうが遥かに知名度がある有名なルートであったし・・。
ありうべき結末であるのかもしれないが、彼のホームページを見て、お亡くなりになるわずか数ヶ月前に書かれた熱っぽい記事を読むとき、山での不慮の死というものの残酷さがひしひしと感じとれて、とても沈痛な心持になってしまう。
彼の自伝的なホームページがどこかに行ってしまわぬように、私のところにリンクをつけた、そして遭難碑に語りかけるように、僕は彼のホームページをときどき開き、彼の熱っぽい文章を胸に刻むのである。・・このリンクは私が一番大切にしているものだ。
僕も、体が動くうちに、彼のような登山がしたいものだと思う。
追記
このホームページの名前「甲武相山の旅」は昭和15年刊行の今井重雄さんの名著からいただいたものであり、右上の狼の図案は、あの宮内敏雄さんの名著「奥多摩」見開きのページからいただいたものである。
そして、私が一番大切にしていることは、昭和初期の原全教氏や、田島勝太郎氏がかって辿った奥秩父の険しい谷を遡行し、いまは崩れて道跡も不明瞭なかっての山道、猟師道を、足跡を求めてさまよい歩くことである。
いろんな先人の残された名著を読み、往時を偲び、それを今に蘇らせる。
私にとって奥秩父は、故郷の山々だから・・そんな営みは自分自身を知ることにつながってくるのだと思う。
その一方で、挑戦なき者は去れ、というのは、かの山学同志会の小西政継さんの気風から受け継いでいる。
これからは、あぶねぇ山屋さんもそんなように自分を引っ張っていってくれる先人の一人に加えることにしよう。
ところで、そんな山の先人たちの存在を私に教えてくれたのは、奥多摩山岳会の天野一郎さんである。天野さんの執筆された奥秩父1の地図(当時)のガイドブックには、この地の先人たちが残した山岳書籍の数々が掲載されており、お蔭で素晴らしい書物に出会うことが出来た。
自分ひとりで何もかも出来るなどと思い上がってはいけない、
偉大な先人の肩の上に立ってこそ、先人よりもすこしだけ彼方が見えるというものである。
さよならの旅路(表妙義) ぐりーんさんのホームページ








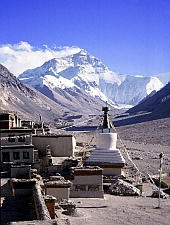
Recent Comments